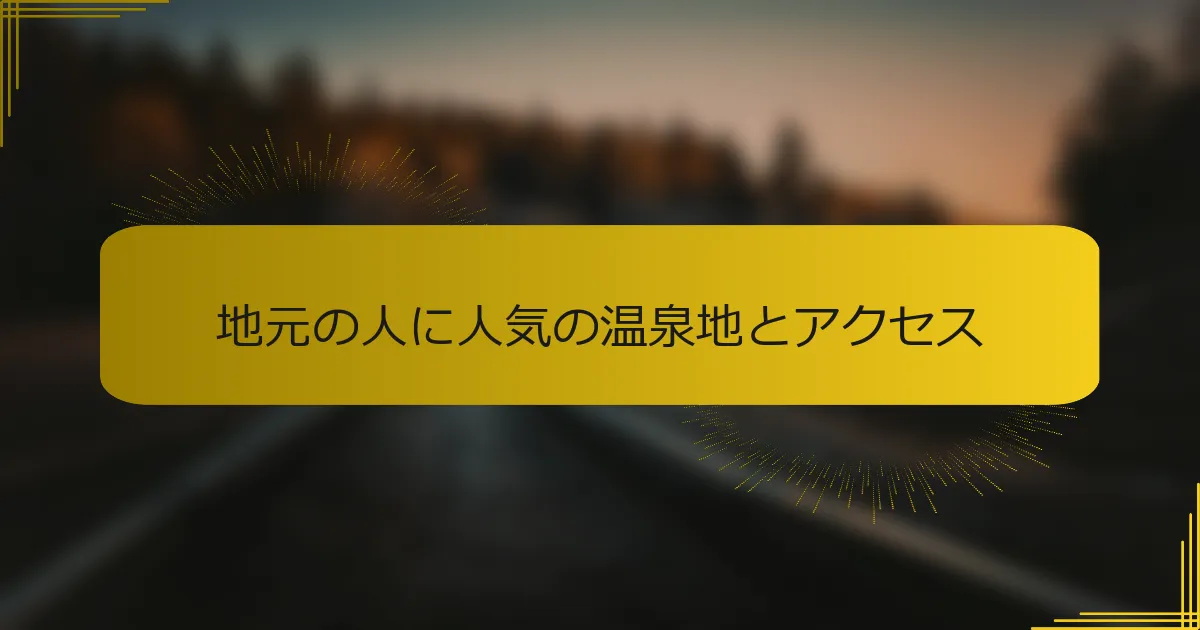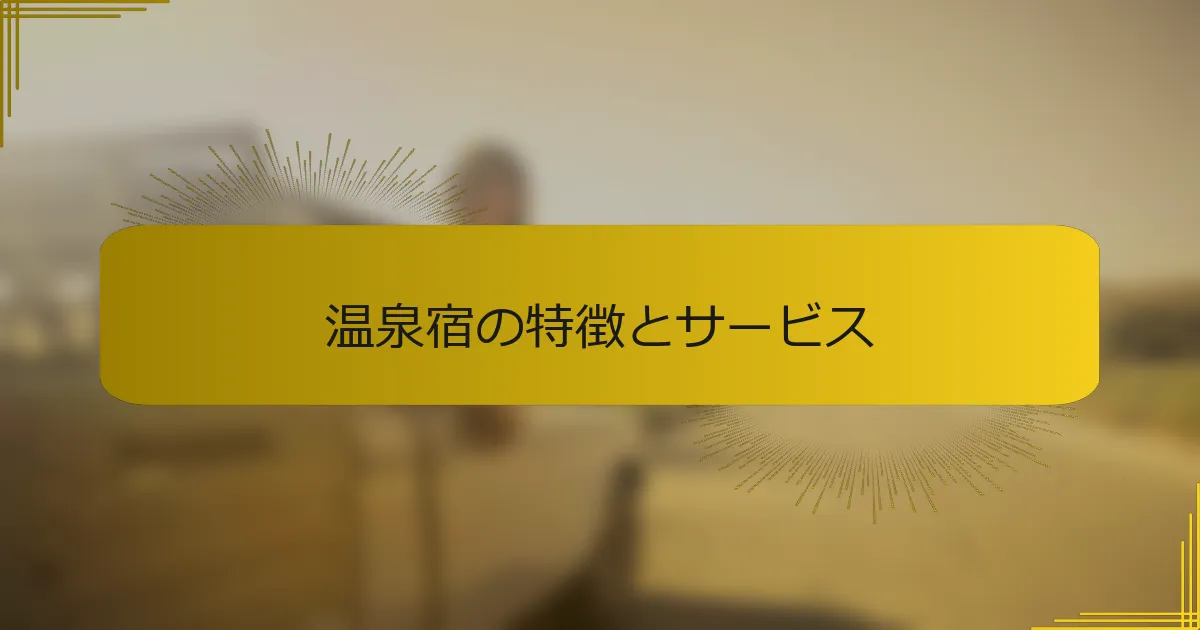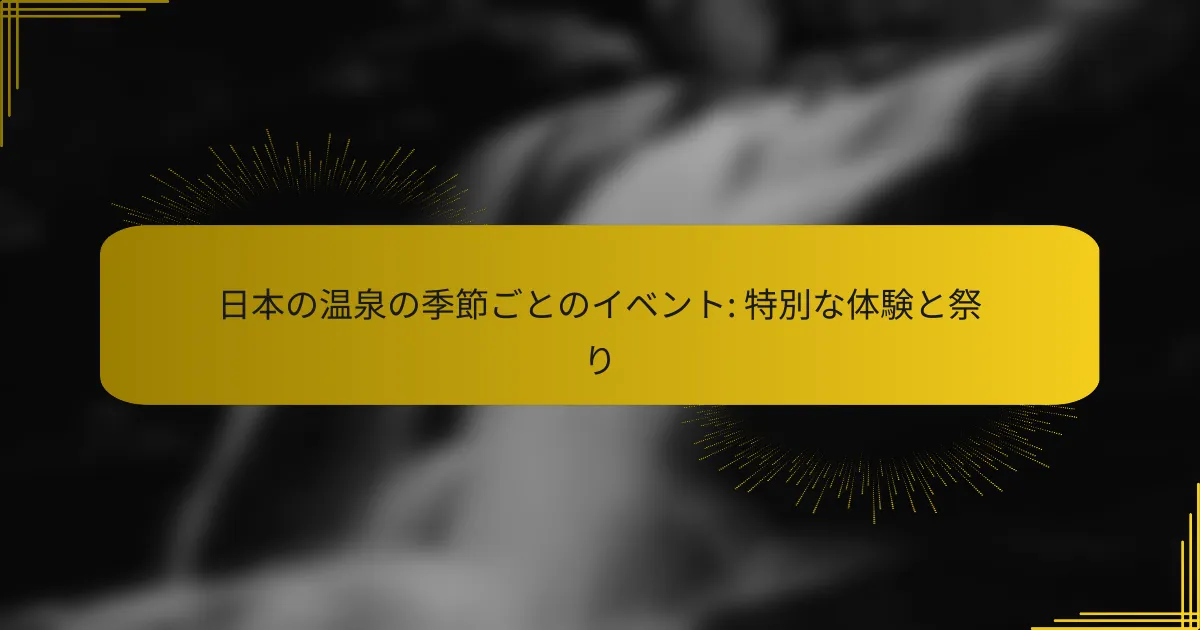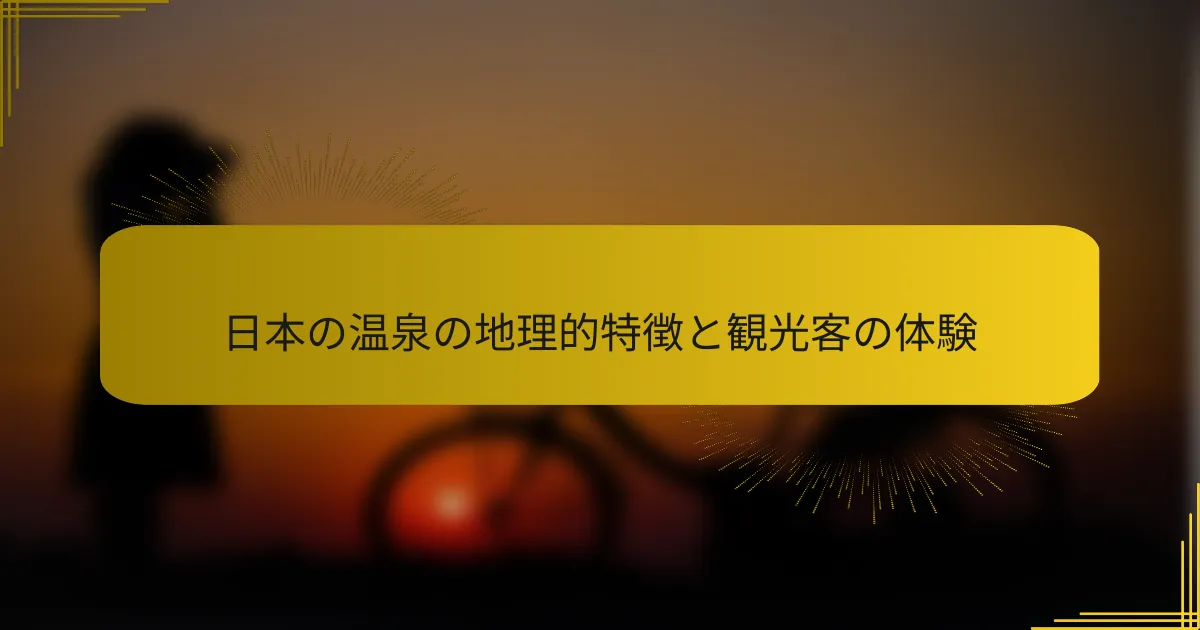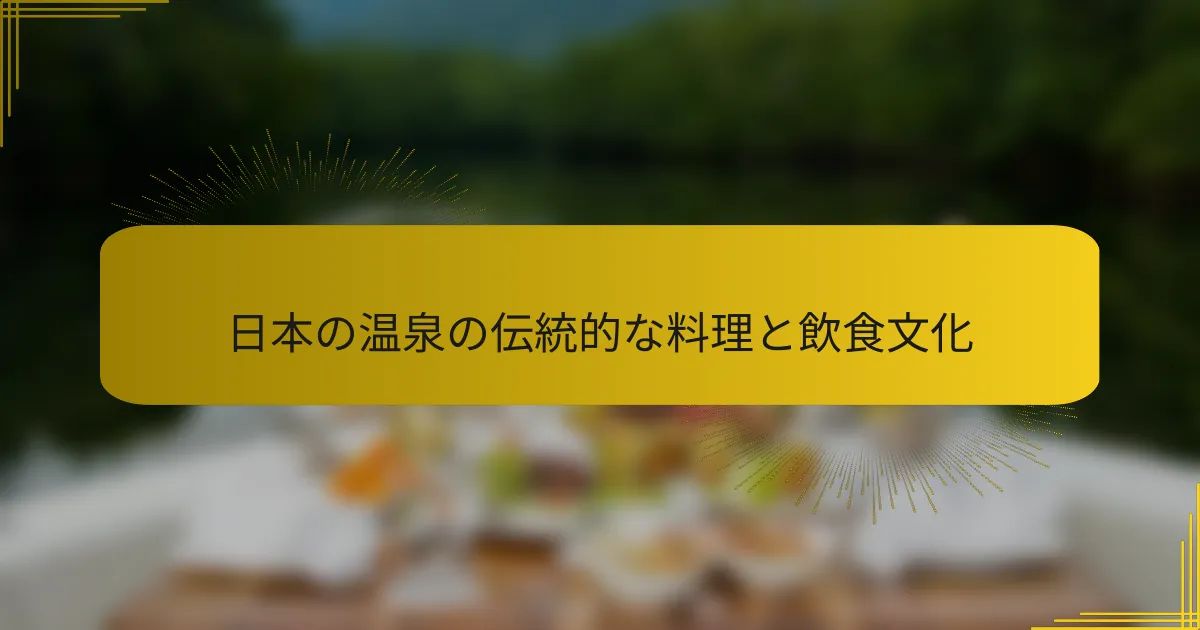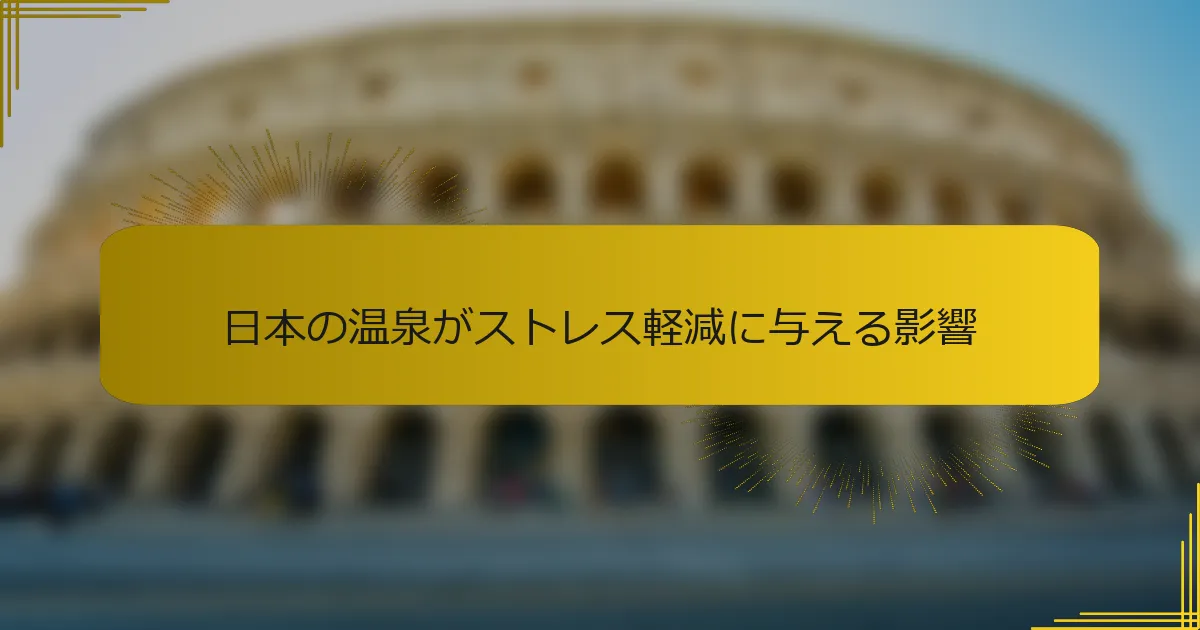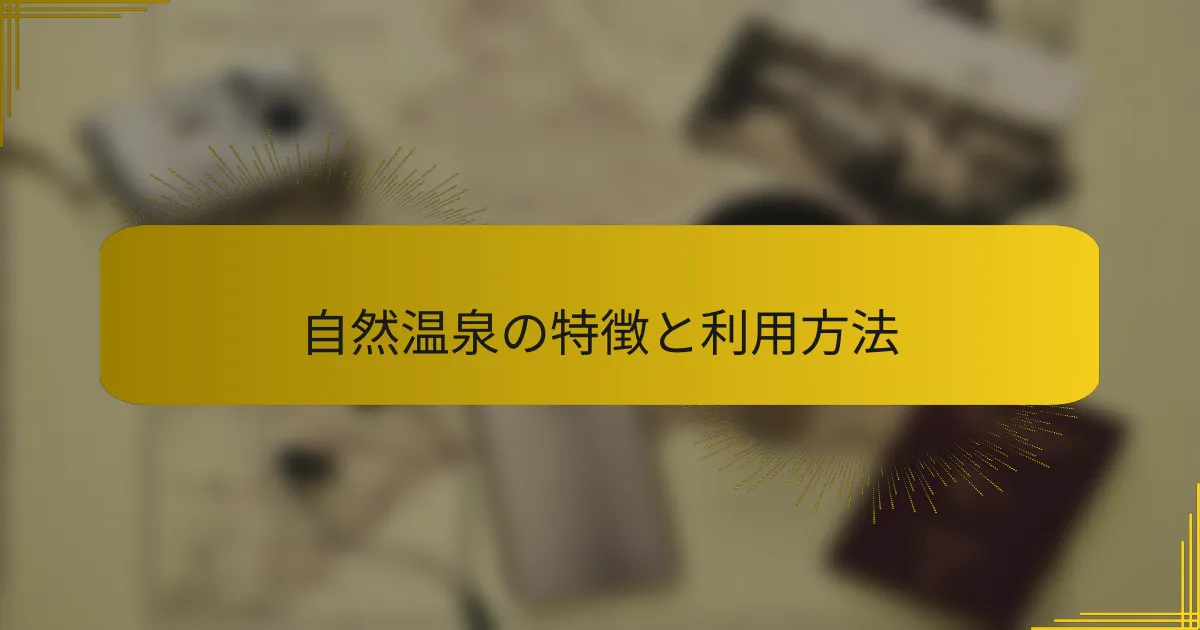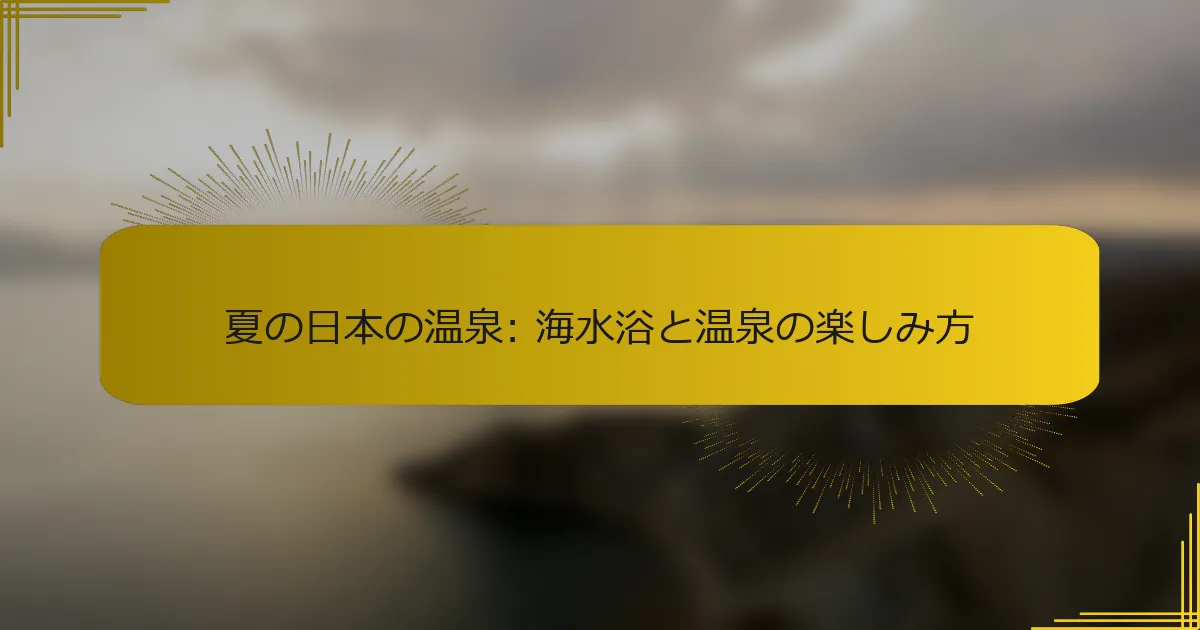Hakone Onsen is a popular hot spring destination located in Kanagawa Prefecture, renowned for its
ふろや.comへようこそ
日本の温泉は、心身の癒しとリラクゼーションを提供する特別な場所です。ふろや.comでは、日本各地の温泉地を紹介し、その魅力と楽しみ方をお伝えします。豊かな自然に囲まれた温泉で、日常の疲れを癒しましょう。
私たちは、地域ごとの温泉の特徴や、地元の文化、魅力的な宿泊施設、さらには温泉に関連するアクティビティを取り上げています。観光情報をもとに、あなたの次の温泉旅行を計画する手助けをします。
探求できる主なテーマ
- 地域別温泉ガイド
- 宿泊施設のおすすめ
- 温泉の効能と健康効果
- 温泉と地元のグルメ
- アクセス情報と交通手段